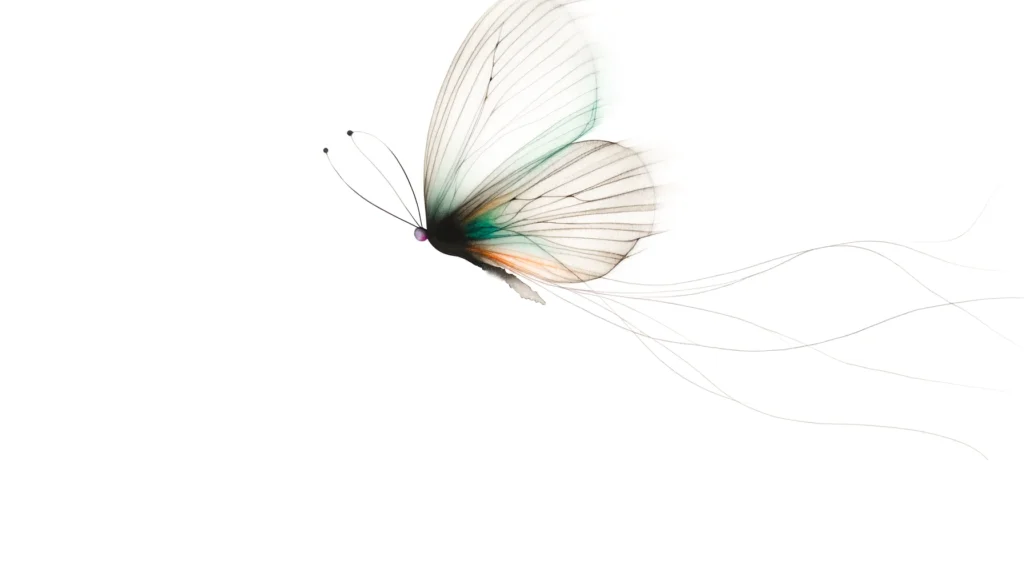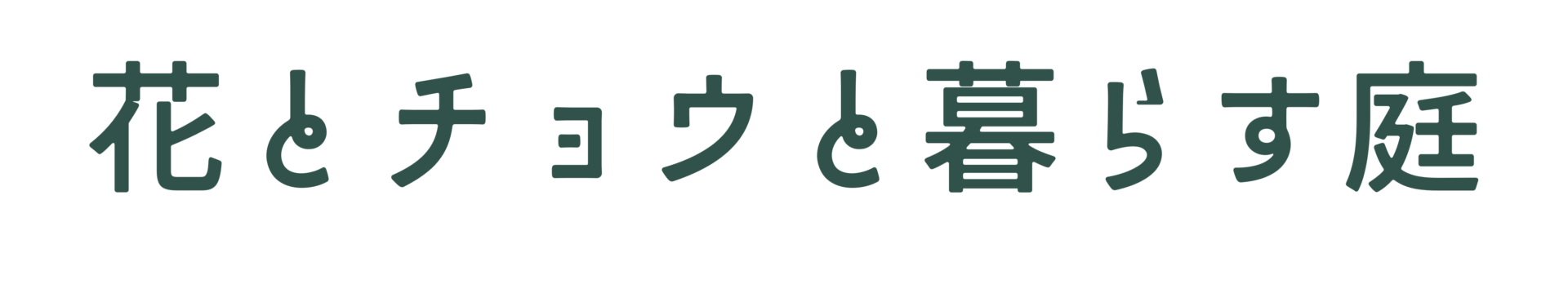蝶の食草|お庭にスミレやパンジーを植えるとツマグロヒョウモンがやって来る!

寒い時期に園芸店を明るく彩っているパンジーやビオラ、可憐な印象のスミレなど、スミレ科の植物はガーデナーにとって馴染み深い植物ですよね。
スミレ科の植物は私たちを楽しませてくれるだけでなく、チョウの幼虫にとって重要な食べ物でもあるんです。
チョウの幼虫は特定の植物を食べて育ちます。
それらの植物は「食草」や「食樹」と呼ばれています。
スミレ科の植物を食草とするチョウにツマグロヒョウモンがいます。
ツマグロヒョウモンは、住宅地の庭やベランダにもやって来る可能性がある「身近なチョウ」です。
もし家のまわりが自然に恵まれた環境であれば、ミドリヒョウモンの姿も見られるかもしれません。
このページでは、スミレ科の植物をガーデンに植えて、ツマグロヒョウモンたちを招くためのポイントを紹介しています。
まず、最も重要なことは、植物を無農薬で育てるということです。
色とりどりのスミレが咲くガーデンに、チョウもやって来る、そんな自然とのふれあいを楽しんでみませんか?
スミレ科の植物について

スミレ科の植物は、世界中に分布していて、特に北半球の温帯地域に多いようです。
スミレやパンジーなどのなじみ深い花が、春にたくさんの花を咲かせている姿をよく目にしますよね。
生態や特徴
スミレ科の植物は森の下草や野原、道端など様々な場所で見られ、よく排水されたやや湿った土を好みます。
日本に自生する多くのスミレ科の植物は、冬になると地上部が枯れて、植物は休眠状態に入りますが、地下には根や球根が残っていて、次の春にまた新しい芽を出します。
園芸種のパンジーとビオラは、ヨーロッパの野生種を原種として育種さたものです。
種子にアリが好む脂肪の塊がついている種類もあり、アリによって広く運ばれることもあるようです。
スミレ科植物を食草とする身近なチョウ

住宅地の庭やベランダにも訪れる可能性がある身近なチョウには、ツマグロヒョウモンやミドリヒョウモンがいます。
それぞれのチョウの生態や生息地を知ることは、ガーデンに招くためのヒントになりますよ。
ツマグロヒョウモン
ツマグロヒョウモンはタテハチョウ科のチョウで、本州から沖縄の、明るく開けた環境に生息しています。
訪花性が高いチョウなので、チョウが好んで蜜を吸う花「蜜源植物」もガーデンに植えておくと、とても喜ばれると思います。
ツマグロヒョウモンの幼虫は、野生種のスミレ科植物だけでなく、園芸種のスミレ科植物も好んで食べます。
卵はスミレ科植物の周辺に産みつけられることが多いようです。
植木鉢の縁や、すぐそばの小枝などに卵が産みつけられているのを見たことがあるよ。
ツマグロヒョウモンの成虫は、地域にもよりますが、4月頃から11月頃まで見られ、年に複数回の発生があります。
他のヒョウモンチョウの仲間の多くが年1回しか発生しないのに対し、多化性である点もツマグロヒョウモンの特徴です。
なのでツマグロヒョウモンの食草は、一年中、需要がありますよ。
終齢の幼虫は体長約30mmで、黒色の体の背中に一本の赤い筋があります。
体中に棘状の突起があり、一見すると危険な毛虫のような印象ですが、実は柔らかく刺すこともなければ毒もありません。
蛹は尾でぶら下がる垂蛹タイプで、背面に金属色の棘状突起が並んでキラキラしています。
ミドリヒョウモン
ミドリヒョウモンもタテハチョウ科のチョウで、北海道~九州の、樹林周囲の草地に生息しています。
ツマグロヒョウモンよりも自然豊かな環境を好みます。
ミドリヒョウモンも訪花性が高いチョウなので、チョウが好んで蜜を吸う花「蜜源植物」もガーデンに植えておくと、とても喜ばれると思います。
幼虫は、野生種のスミレ科植物を好み、園芸種のスミレ科植物は好まないようです。
ミドリヒョウモンは年に1回の発生で、活動期間は6月から10月ですが、夏の暑い時期は休眠するので、飛んでいる姿が見られるのは初夏と秋です。
幼虫や蛹の姿は、ツマグロヒョウモンに類似します。
卵は樹の上などから食草の近くに産み落とされるようです。
ただ、ミドリヒョウモンは、よほど自然豊かな環境でなければ庭での発生は難しいかもしれません。
ツマグロヒョウモンについては、下の記事で詳しく紹介しています。
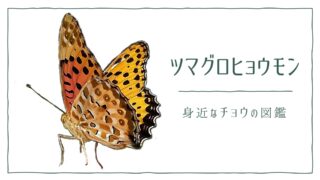
スミレ科植物の入手と栽培と管理

日本にはいろいろな種類のスミレが自生していて、特になじみ深いのは「スミレ」と「タチツボスミレ」ではないでしょうか?
また、冬のガーデニングの定番ともいえるパンジーやビオラも広く愛されていますよね。毎年ガーデンに植えて楽しんでいるという方も多いと思います。
チョウを招くための食草という観点から選ぶ場合、ある程度の量が必要となるので、身近で手に入りやすいという条件も重要になります。
食草としてガーデンに迎えるには、やはり次の植物が適していると思います。
- スミレ
- タチツボスミレ
- パンジー
- ビオラ
野生種のスミレとタチツボスミレ

野生種であるスミレやタチツボスミレは、春に美しい深紫色の花を咲かせる多年草です。菫色なんて表現があるほど親しまれていますよね。
日当たりの良い草地や道端、土手などで自生しており、日本全国どこでも見られます。
街なかでもコンクリートの割れ目から顔をのぞかせているのを見かけたことがありませんか?
スミレの葉は細長いへら型で、タチツボスミレの葉はハート型です。
スミレは草丈が約10センチメートル、タチツボスミレは20センチメートルくらいになるでしょうか。
野生種の入手
園芸店などで花が咲いた株が春に出回りますが、山野草扱いで高価なものも多いかと思います。
株もまだ小ぶりな状態で、食草とするにはじっくり育てた後になるでしょう。
そこでおすすめなのが、道端で見かけたスミレの種をもらってきて蒔く方法です。野生で見かける品種はたくましいものが多いので、育てやすく、株の量も確保できると思います。
菫色の花は春にしか咲きませんが、その後も自家受粉する閉鎖花が咲いているようで、春以降も種が採取できます。
野生種の栽培方法
スミレやタチツボスミレはその可憐な花の印象とは対照的に、意外と丈夫で育てやすい植物です。
- 加湿にならないように用土や水やりに注意する
- 蒸れないように風通しにも配慮する
- 日当たりを好むが、真夏の直射日光は避ける
これらのポイントに注意すれば、毎年、春には美しい花が楽しめますよ。
野生種の種まき
スミレやタチツボスミレを増やす方法には種まき・さし芽・根伏せ・株分けなどがあります。
一般的なのは種まきでしょうか。
スミレ科の種は、小さな果実の中に入っていて、熟すと勢いよく飛び散ります。
果実が上を向いてきたら完熟間近です。
完熟で採取した種と未熟で採取した種では、適切な種まきの方法が少し違うようです。
完熟種子は一度低温に当たらないと発芽しないらしく、冷蔵庫などでしばらく寒さにあててから蒔くと良いようです。
未熟種子は、とりまきで良いようです。
種を蒔くときは次の点に注意して、挑戦してみてください。
- スミレやタチツボスミレの種は好光性なので、浅蒔きする
- 発芽するまで1週間くらいかかるので、その間、種を乾かないように霧吹きなどでやさしく水をやる。
- 本葉が出るまでは直射日光を避けた明るい場所で管理する。
また、大きく育った株がある場合は、植え替えの際に自然に分かれる部分で株分けして増やすと良いですね。
園芸種のパンジーとビオラ

パンジーとビオラは、ヨーロッパの野生種を原種として育種され、かつては花の大きさで区別されていましたが、現在では多くの交雑種が存在し、明確な区別は困難になっています。
現代の品種は秋から春にかけて長期間花を咲かせるように改良されています。
園芸種の入手
園芸店では10月頃からポット苗が並び始めます。
パンジーやビオラはお手頃な値段ですし、大株に育っている苗を購入することもできます。ガーデナーにとってありがたい環境が整っています。
しかし、購入してきたものをすぐに幼虫へふるまうことはできません。
多くの苗には農薬がかけられているので、その葉を食べた幼虫は弱ってしまうでしょう。
私は専門家ではないのではっきりしたことは言えませんが、秋に苗を購入して植え付けて、冬を越し、春以降になったら、提供しても大丈夫かもしれません。
私のガーデンでは、秋に購入した苗を、春から初夏の期間に食べた幼虫は無事に育っているように見えます…。
ただ、実際のところはわからないので、自己判断でお願いします。
おすすめなのは、こちらもやはり種まきです。
パンジーやビオラは目移りするほどたくさんの種類の種が販売されていますよね。
苗ではあまり見かけないような変わった品種の種もあって楽しいです。
また、自分で種を採取して、次のシーズンに蒔くのもおすすめです。
交配されているF1種は親と同じ形質にはなりませんが、どんな花が咲くのかもまた楽しみです。
園芸種の栽培方法
パンジーやビオラはとても人気があるため、多くの栽培情報があって、心強いですよね。
次のポイントに注意すれば、来年の初夏まで、次々と美しい花を咲かせてくれますよ。
- 苗を買う場合は、10月下旬から11月の適期に購入する
- 日光を好むため、日当たりのいい場所に植える
- 加湿にならないように用土や水やりに注意する
- 蒸れないように風通しにも配慮する
- 花期が長いので、適切に施肥する
夏期に涼しい環境を整えられる場合、夏越しもできるようです。
園芸種の種まき
パンジーやビオラは種まきやさし芽で増やせます。
こちらも一般によく行われているのは種まきでしょうか。
パンジーやビオラの種まきの難易度は少し高めだというイメージがありませんか?
園芸店で出まわる株のように、年内の内からたくさんの花を咲かせようと思うと、晩夏には種まきを始めなければ間に合いません。
日本の晩夏はまだまだ暑く、パンジーやビオラの種の発芽適温である20℃前後の環境をつくりだすのは一苦労です。
気温だけでなく日光の問題もあります。
クーラーボックスなどで温度を管理し発芽させたとしても、その後日光をしっかり当てて育てないとすぐに徒長してしまいます。
日光を当てたいが、暑いのはダメ…、なかなかの難問で、挑戦されている皆さんは工夫を凝らされています。
そういった要因から、パンジーやビオラの種まきの難易度は少し高めな印象なのだと思います。
ただ、食草としてパンジーやビオラを育てるのであれば、年内に花を咲かすことにはこだわらなくともよいので、難易度は下がります。
秋になって発芽適温の時期になってから種を蒔けばいいのですから、温度管理も日光浴も自然におまかせです。
あとは野生種同様、次の注意点をおさえて挑戦してみてください。
- パンジーやビオラの種は好光性なので、浅蒔きする
- 発芽するまで1週間くらいかかるので、その間、種を乾かないように霧吹きなどでやさしく水をやる。
- 本葉が出るまでは直射日光を避けた明るい場所で管理する。

年間を通じた食草管理
ミドリヒョウモンは年に一世代を繋ぐチョウですが、ツマグロヒョウモンは年に数世代を繰り返す多化性の蝶です。
多化性のチョウにいつでもおいしい食草を提供するためには、年間を通した食草管理をしなければなりません。

食草の提供スケジュール
植物はそれぞれ生育条件が異なります。
そんな植物の生態を踏まえつつ、年間スケジュールを組んでいきます。
スミレ科の場合、スミレやタチツボスミレなどの野生種は、適切な環境下であれば夏に枯れることはありませんが、冬には休眠してしまいます。
一方で、パンジーやビオラなどの園芸種は冬の寒さの中でも元気ですが、夏には弱って枯れてしまうことが多いですよね。
これらの植物の特性をうまく組み合わせることで、一年中チョウに食草を提供できる環境を整えることができます。
スミレ科の場合、春は園芸種、初夏~秋は野生種、晩秋は園芸種とバトンタッチするのが理想的ではないでしょうか。
ツマグロヒョウモンたちは幼虫の姿で越冬しますが、真冬はあまり食べていないように思います。
冬の寒さからの隠れ家としても園芸種に活躍してもらいましょう。
食べられた食草の回復
スミレ科植物の株がまだ小さい場合、ツマグロヒョウモンやミドリヒョウモンの幼虫にぺろりとたいらげられて丸坊主になってしまうこともあります。
チョウの幼虫に食べられてしまった食草は、一時的に回復期間を設ける必要があります。
しばらくの間養生させて、再び葉を茂らせ、株が元の大きさに戻るまで保護してあげましょう。
新たに卵が産み付けられないよう、回復中の植物にはネットなどをかぶせてあげると効果的です。
私のガーデンのタチツボスミレは、年に二回も丸坊主にされてしまっても、翌年の春には花を満開に咲かせてくれます。
植物はすごいですよね。

食草の提供方法のアイデア
ここで問題になって来るのは「植物が養生している間にツマグロヒョウモンが訪ねてきたらどうしよう」ということですよね。
この解決法としては、食草の量を増やすか、小出しに提供するすることが考えられるかと思います。
私の場合、パンジーやビオラほど数が揃えられないスミレやタチツボスミレは主に鉢植えで育てていて、
数鉢をローテーションでチョウに提供しています。
また、地植えのものも少量用意しておき、鉢から移動した幼虫のための救済場所としています。
幼虫が蛹になる前に食草が尽きてしまうと、申し訳ない気持ちになってしまいます。
あちこち探し回って入手できればよいのですが、できないときもあるでしょう。
食草の量を適切に管理し、チョウの幼虫がいつでもおいしい葉を食べられる環境を整えることが、ガーデンでチョウを楽しむための一つの鍵となります。
まとめ

スミレ科の植物を庭やベランダに植えることで、美しいツマグロヒョウモンやミドリヒョウモンなどのチョウを招くことができます。
この記事では、スミレ科植物の選び方、栽培方法、種まき、年間を通じた食草の管理法などを、ご紹介してきました。
「ツマグロヒョウモンたちの役にも立つといいな」と育てた無農薬のスミレ科植物に、実際にチョウがやってきて、卵を産んでいるのを目撃するのは感動的です。
しばらくして、卵が孵化し、小さな幼虫がおいしそうに葉を食べているのを見ると、このガーデンづくりに充実感を覚えると思います。
バタフライガーデンづくりを始めるためのガイドとして、この記事が役立てば嬉しいです。
バタフライガーデンづくりの最初の一歩はこちらの記事からどうぞ。

お庭やベランダにもやって来る「身近な蝶」を扱った記事を一覧で紹介しています。
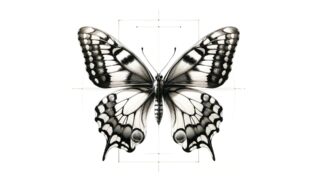
蝶に人気の蜜源植物のひとつである「コスモス」「ランタナ」「ブッドレア」の記事です。